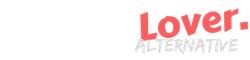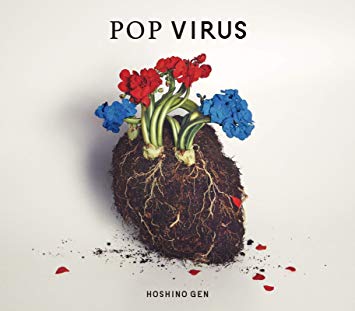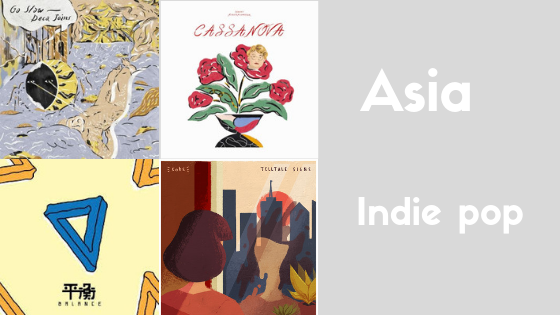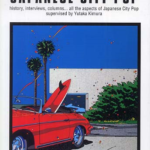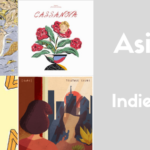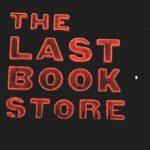毎月少なくともアルバム数枚は音源を買い漁っているなかから、炭酸おすすめの音楽を紹介します。
今回はとにかく「おしゃれで都会的、夜ドライブしてて聴いたらテンションが上がる音楽」というテーマで選びました。
特にこんな人に読んでほしい記事です。
- 純粋に新しい音楽やバンドを開拓したい
- ドライブする時に聴くとワクワクする音楽を探している
- オシャレな音楽を聴いて気分を高めたい
一緒に聴いていただけたら幸いです。
Nulbarich 和製ブラックミュージック
「It's Who We Are」
まず、このNulbarich(ナルバリッチ)は、近年ブレイクしてるSuchmosと双璧を成すんじゃないかと思っている。
(Suchmosは某自動車メーカーのCMで曲が流れてたりするので、こちらのほうが聴いたことある人が多いかな?)
Suchmosの詳細は、シティ・ポップ リバイバルで注目されてるSuchmosとceroだけど、音楽性やルーツの違いについて考えた。で書いてます。
ただ、音楽性としてはNulbarichのほうがブラック色が強い。
冒頭から流れるギターのカッティングからすでにオシャレな雰囲気が漂ってくる。小気味の良いテンポでわくわくするねー。
Suchmosもそうなんだけど、クラップ(手拍子みたいな音)が要所でよく使われてる印象。
この曲についてはラテン音楽でよく使われるクラーベのリズムで、8ビートにクラーベのリズムが重なって音にうねり(グルーヴ)が生まれる。
全体を通してよく聴いてみると、一曲の中でいろんなリズムが変化して絡み合っているのだ。
まぁ難しいことは置いといて、単純に聴いてて気持ち良いのでおすすめ!
バンド名の由来もなにやらかっこいいじゃないか...
ファンク、アシッド・ジャズなどのブラックミュージックをベースに、ポップス、ロックなどにもインスパイアされたサウンドは、国内外のフィールドで唯一無二のグルーヴを奏でる。
Nulbarich( ナルバリッチ) という名前には、
Null( ゼロ、形なく限りなく無の状態)
but( しかし)
Rich( 裕福、満たされている)
から作られた造語であり、形あるものが全てではなく、形の無いもの
(SOUL、思いやりや優しさ含めた全ての愛、思想、行動、感情)
で満たされている「何も無いけど満たされている」という意味が込められている。
【その他おすすめ曲】
NEW ERA
Awesome City Club 魅惑のツインボーカル
「Don't Think, Feel」
男女ツインボーカルのずるさよ・・・
あざといけどかっこいい。ずるい。(2回目)
同じ曲でもボーカルが2人いると表現の幅が広がる。ずるい。(3回目)
![]()
「架空の街 Awesome Cityのサウンドトラック」をテーマに、テン年代のシティポップをRISOKYOからTOKYOに向けて発信する男女混成5人組。
クラウドファンディングやVRなど最新のテクノロジーを積極的に駆使した活動が各所から注目を集めている。
そうそう、クラウドファンディングの大手CAMPFIREでCD制作費を集めたりしていて、そのリターンもいろいろ種類があって人気のようだ。
実際に会って交流できたり限定音源がもらえたり、ファンにとっては嬉しいリターンをたくさん用意してくれていた。
バンドやアーティストもクラウドファンディングを活用する人が増えている。
いまはディスクや音源が売れにくい時代だから、そういう仕組みも上手に使って好きなアーティストを応援したいものです。
【その他おすすめ曲】
アウトサイダー
涙の上海ナイト
この涙の上海ナイトは、歌詞は頭空っぽの語感のみ。耳障り重視!
だがそこが良い。手法がサザンオールスターズ的である。
Tempalay 漂う浮遊感
「革命前夜」
西海岸やカナダの海外インディーシーンの影響を感じさせる極彩の脱力系サウンドに中毒者が続出。
話題と注目が集まる中で2度目の出演となったFUJI ROCK FESTIVAL’17では、小原がワクワクしすぎて右指を骨折。
そんな緊急事態に仲間のギタリスト達が集結し、1曲ずつギターをバトン代わりに演奏したステージが多くの人の胸を打ち、ちょっとした伝説となる・・・!
ワクワクしすぎて右指を骨折。
サウンドが脱力系なだけにいろいろゆるいのかな(笑)
わかりやすく近いバンドを挙げると、ポストゆらゆら帝国とか言われていますね。
音に浮遊感があって、歌も力が抜けていて、ちょうど良い。
夜になって急に甘いものが食べたくなって、あえて少し遠くのコンビニまでドライブしようか。
日常でも思わぬところでちょっと高揚する瞬間にぴったりなんじゃないかな。
音楽を辿る楽しさ
今回紹介したNulbarich、Awesome City Club、Tempalayの3バンド、今後はどんな新しい曲を届けてくれるでしょうか。
彼らが影響を受けてきた音楽を掘ってさかのぼっても、きっと新しい出会いがある。
また視点や切り口を変えつつ、音楽を紹介しようと思います。
こちらの記事もおすすめ。